こんにちは、食べたいものが多すぎて収拾がつかなくなっている、ため子です。秋って美味しいものが沢山出ますよね。さつまいもに栗に柿に秋刀魚…。そのうえ限定スイーツもたくさん出て来て困ってしまいます。
さて、今日は電気のアンペア数についてお話したいと思います。引っ越しをすると色々なことをしなくてはならないですよね。転出届に転入届、水道・ガス・電気の切り替え…。その中でも、最適な電力のアンペア数についてお話したいと思います。
ちなみに、私は引っ越し前の賃貸物件のアンペア数は20Aでした。コンロはガスではなく、IHクッキングヒーターを使用してました。同居人が居たので、相手が調理や温めをしている時にドライヤーを使ってしまうと、ブレーカーが落ちてしまうということがよくありました。同時に家電を使っていたわけでもないのにブレーカーが落ちてしまったり…。それが結構…、いや、相当ストレスになっていました。物件によってはアンペア数を変えることのできない場合もあるので、引っ越しの際はきちんと確認することが大切です。
アンペア数とは
電気のアンペア数とは、電流の大きさを表す単位です。 電流とは電気の流れの量を意味します。アンペア数が大きいほど電力が多く流れるため、一度にいくつもの家電を使用することが出来ます。
オール家電の物件ではアンペア数が高く設定する必要がありますし、夏は多くの電力を消費するので自分の生活に合ったアンペア数を設定することが必要です。契約アンペアは数は10A、15A、20A、30A、40A、50A、60Aと設定することが出来ます。
主な家電のアンペア数
エアコン:冷房運転時4~10A、暖房運転時5~15A(100Vのエアコンの場合)
冷蔵庫:1~3A(100Vの場合)
洗濯機:3~10A(100Vの場合)
・全自動洗濯機:洗濯時2~5A、脱水時4~8A
・ドラム式洗濯乾燥機:洗濯時3~10A、乾燥時10~15A(機種によってはそれ以上かかる場合も)
・二層式洗濯機:洗濯時2~4A、脱水時4~7A
電子レンジ・オーブンレンジ:5~15A
ドライヤー:5~15A
電気ケトル:8~15A(100Vの場合)
※機種によって異なるので、製品のラベルや本体に記載されている定格電流を確認してください。
最適なアンペア数は?
もちろん、アンペア数が低ければ低いほど電気の基本料金は低くなります。しかし、その分一度に使える家電の数は限られてしまいます。例えば、20Aに設定していると仮定します。エアコンを使用しながら電子レンジを使用すると、使っている機種によってはブレーカーが落ちてしまう可能性があります。高めに設定していると安心感はありますが、自分が使うアンペア数よりも高く設定している可能性があります。そうすると、無駄に電気代を支払っていることに繋がります。電気代は毎月支払うものですから、出来るだけ抑えたいですよね。
冬と夏では使う電力に差があるでしょう。それぞれ最適なアンペア数に設定したいところですが、基本的には契約期間や変更制限がある場合があります。上げるのは可能だけれども、下げるのは1年間出来ないという制限もあります。そのため、自分の使う家電を調べてアンペア数を設定することが大切です。
結果として
家庭によって最適なアンペア数は様々です。ちなみに、私は一人暮らしでアンペア数を30Aに設定しています。理由は、夏にエアコンを使って、ケトルやオーブンレンジ同時に使うことがあるからです。
基本的にはエアコンを使う世帯は30A以上にしているところが多い印象です。もちろん、電気代を抑えるために同時に使用する家電を控えて、アンペア数を下げて設定することで節約をするのも良いでしょう。しかし、毎日気を付けながら生活をするというのは中々大変な部分があります。
最後に
いかがでしたでしょうか。過ごしやすい空間を作るためにアンペア数の設定は大切ですよね。一度設定すると中々変更することが出来ないので慎重に考える必要がありますが、毎日の生活で不便があるというのはストレスにもつながります。自分が同時に使う家電を考えながら決めていきましょう。それでは、また。

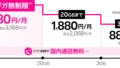
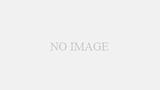
コメント